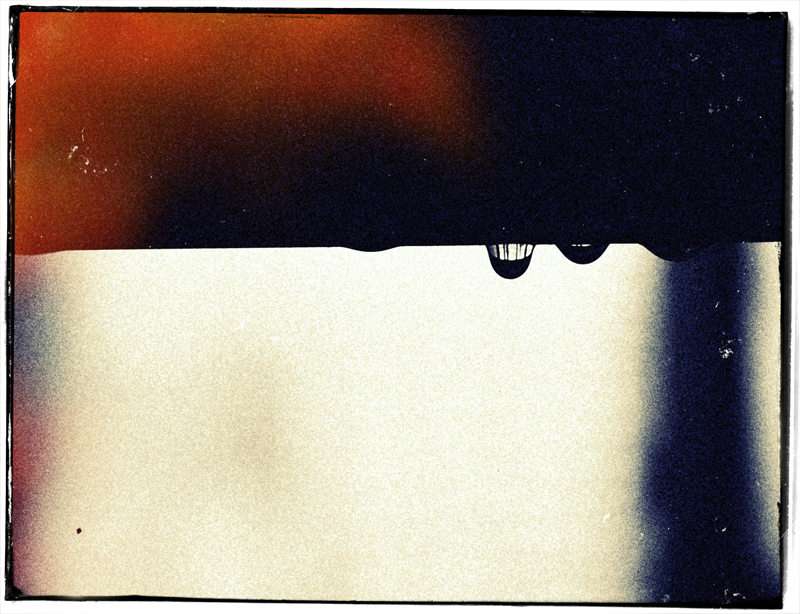斜交いの家の金木犀がすっかり散り終わると、季節は秋から冬へ衣替えを始める。時計の針が正午を回った辺りから降り出した雨のせいで、いつもより今日は一段と夕暮れるのが速いようだ。じきに黄昏てしまうだろうその一歩手前で、私は珈琲をいれることにした。CDは何をかけようか、読みかけの本を手元に引き寄せながらあれこれ考えるひとときはとても心地よい。
とその時呼び鈴が響いた。宅急便か何かかと思って勢い良く扉をあけると、そこに立っていたのは宅急便屋の兄ちゃんでも新聞集金のおばちゃんでもなく、恐らく私と同じ年頃の女の人だった。雨の中を長いこと歩いてきたのだろう、上着のあちこちに雨の雫がまばら模様を描いており、片手には傘が握られている。思い掛けない来客を前に、私は無言のまましばしその立ち姿を眺めていた。
「やっと見つけたぁ」
親しげに、その女の人が笑う。
「探したんだから。引越したなんて知らなかったし」
そりゃそうだろう。私はここに引っ越す際、数える程の知人にしか住所を教えなかった。だから、ここまで私を訪ねてやってくる人はとても珍しい。
いや、そんなことはとりあえずどうでもよいのだ。あなたは誰ですか、と問い掛けなければならない。私は彼女の顔に見覚えがなかった。
「これ、買ってきたから一緒に食べよう」
突然の訪問者に戸惑っている私にお構いなく、彼女はそういってにっこり笑った。何故だろう、その時、とても懐かしい笑みに会った気がして。何故だろう。分からない。彼女がそのまま部屋の中へ入って来るのを、私は止めることができなかった。
「あ、珈琲入れてたんだ。タイミングよかった。ねぇ、チーズケーキなの。さをり、好きでしょう?」
確かに。私はチーズケーキが好きだ。しかも、彼女の差し出した箱を恐る恐る開けてみると、私が一番好んで食べる店のチーズケーキが二つ、並んでいる。
「ありがとう」
一応、そう言ってみた。いや、気付いたら言っていた。ありがとう。よく分かったね、このチーズケーキ、私が好きだってこと。
「覚えてるよぉ、ちゃんと。何かいいことあるとここのチーズケーキ食べたいってよく言ってたじゃない」
私はびっくりした。突然の来客にも驚いたが、今はそれじゃない、そうじゃなくて、今のこの、彼女の返事にだ。私は今彼女にありがとうと言ったが、それ以上のことはまだ口に出していなかった。ありがとうとは確かに言ったが、それに続いて言葉をまだ口に出してはいなかったのだ。なのに彼女は私が続いて言おうかどうかと思った言葉に対して今、返事を返してきた。何故分かったのだろう、何故。私はすっかり自分のペースを失っていた。どうなっているんだろう、一体、いや、ともかくも落ちつかねば。見覚えの無い彼女をすでに部屋にあげてしまったのだからここまではもういい、もういいが、さて、これからどうしよう。
何せ、今私に分かっていることは、彼女が私のことをそれなりに知っている人物だろうということだけなのだ。
箱の中のチーズケーキが遠慮深げに私を見上げている。
「ね、ケーキ食べよう。珈琲、半分もらってもいい?」
彼女はあいかわらずやんわりと笑んでいる。私は促されるまま、チーズケーキと珈琲を二人分、テーブルに載せた。
「あれからどうしてた?」
彼女が尋ねる。
「あれからっていつから?」
当然尋ね返す私に、彼女は淀みなく言葉を返してくる。
「会わなくなってから。私気になって気になってしょうがなかったんだ。ずっと。ね、そういえば、あの時のカレとは別れたの?」
「あの時のカレって?」
「ほら、あの人だよ、なんかいつもテンション高い人。剣道やってて、さをりを笑わせるのに必死って感じの」
「…あ、あぁ、あの人かぁ。うん、別れちゃったよ。でも何、すんごい昔の話じゃん、それって」
「そうかなぁ?」
「だって、大学の時だよ、それ。別れたのだって卒業前だったし」
「そうだっけぇ? そっかぁ、別れちゃったかぁ。いい人だと思ったんだけど」
「うん、いい人だった。素敵な人だった。一緒に暮らすことはできなかったけど」
「そっかぁ、うん、そっかぁ。じゃ、いいや。そうだ、ねぇ、あれ、覚えてる?」
「何?」
「終電ツアー」
「ちょっと、それもかなり昔の話じゃない」
「よくやったよねぇ、あれ。毎日終電でこっそり出てきてさ、町うろついて」
「そうそう、でさ、午前三時過ぎに公園で石蹴りやって遊んでたら、公園の前のバーのあんちゃんがいきなり出てきて怒鳴ってさ。女の子がこんな時間に何やってんだって」
「そうそう。お説教されて、ついでにバーに三人引っ張られて、始発になるまでここにいなさい、だって」
「ね、それで、カウンターにいたあんちゃんのカノジョらしき人がまた強烈だったんだよね。真っ赤な髪の毛がぼわぼわで化粧もどぎついんだけど、喋る声がカナリヤみたいなの。啄むみたいに喋るの」
「うんうん、あの声、一度聞いたら忘れられない声だよねぇ」
「結局、それからは、終電ツアーの時には必ずそのバーに最後寄ることになったっけ」
「おいしかったなぁ、カルーア・ミルク」
「おいしかったねぇ、あの時のは」
「初めてだったんだよね、三人とも。お酒」
「私、カルーア・ミルクって、そういえば、あれ以来飲んでないなぁ」
「私一度だけ飲んだけど、途中で止めた。だってマズイんだもん。あの兄ちゃんの作ったのを一度でも飲んだらもう他では飲めない」
「そうだねぇ」
「高校時代のささやかな思い出だね」
「ふふふ」
そう、三人。三人で高校時代、私たちは、ちょうどこの秋から冬になる季節に終電ツアーなるものを毎日のように繰り返していたことがあったのだ。京子と私と…。京子と私と、あと誰だっけ。私はもう一度記憶を辿り直す。京子と私と…。どうしても名前が思い出せない。顔は、そうだ、顔は確かに、今目の前にいる彼女の顔だ。そうだ、そう、彼女は三人目の誰かなのだ。誰、名前は。私は何度も何度も記憶を辿り直す。けれどやっぱり。思い出せない。
私は、目の前で今珈琲を飲んでいる彼女の横顔に見入った。確かにこの顔なんだ。彼女なんだ、三人目は。三人目。彼女は誰。その彼女とは私はいつ知り合いになってどんなふうに付合ってきて、終電ツアーなんかを一緒にやるようになって、しかも大学時代つきあったカレのことまで彼女に紹介して、そんなふうにつきあってきていたんだろう。彼女にまつわる記憶が、すっぽりと私の中から抜け落ちていた。何度穴を覗き込んでも穴は穴だった。空っぽでしかなかった。
「ねぇ、さをり」
彼女が、珈琲カップをテーブルに置いて、私の方を見ないまま言った。彼女の座る位置の正面は窓。多分窓からは、向かいの通りのマンションと、その隣の小さな家の、散り終わった金木犀の木が見えているはず。
「あの時言えなかったけど」
徐々に徐々に小さくなってゆく彼女の声は、それでもはっきり耳に響いてきた。いや、耳にというより、耳の奥から響いて来るようだった。私は彼女の横顔に見入っている。彼女は窓の外を、正面を向いたままじっとしている。
「ずっと言いそびれてて」
彼女の横顔が僅かに歪んだ。
「ごめん」
静止した部屋の中、時計だけがカチカチと音を刻んでいる。もしその音もなかったら、もし彼女の瞼が瞬きもしなかったら、この部屋は時間からぽっかり取り残されてしまいそうだった。
私には、分からなかった。何がごめんで、何が悪かったのか。彼女が誰なのかもまだ、私は確かめていないのだ。何よりもまず彼女に尋ねなくてはいけない。あなたは誰れですか、私の何ですか。どうしてこの場所が分かったのですか、どうして今日ここに来たのですか。
はりついた喉を開くことができないままの私と、私の前で瞬きだけを繰り返しながらそこに座っている彼女と。そして唐突に沈黙は溶ける。
「やだ、もうこんな時間じゃない。私、帰らなくちゃ」
ようやく顔をこっちに向けたかと思ったら、彼女は私の背後の壁にかかっている時計に気付いて立ちあがった。そういえばもう、部屋には灯りを点さなければならないくらいの翳が広がっている。
「珈琲ご馳走様。おいしかった」
彼女はそう言って、そそくさと玄関の方へ向かって行く。
「ねぇ、ちょっと」
「何?」
「あのさ」
私は言いかけて、でも続かなかった。あなたは誰ですか、と、今更彼女に問うことがどうしても躊躇われた。
「何?」
彼女が私の顔を覗き込む。私は。
「…なんでもない。気をつけてね。チーズケーキ、ありがと」
結局声にはできなかった。聞きたいと思ったことの何一つ。
彼女はしばらく黙ったまま私の顔を見ていたが、やがてここにやって来た時と同じ笑みを浮かべてこう言った。
「じゃ、またね」
玄関の扉がぱたんと音を立てて締まった。しばしそこに立ち尽くしてただ締まった玄関の扉を見つめていたものの、何から順番に紐解いていけばいいのだろうとぐちゃぐちゃになった頭を抱えあぐねていた。そしてふと、扉のすぐ脇に立てかけてある見なれない傘に気づいた。
「あ」
忘れていったんだ。彼女が。私は急いでその傘を持つと玄関を走り出た。階段を駆け下り、表通りまで走った。けれど。
彼女の姿はもう、何処にもなかった。
その夜、私は、久しぶりに、本当に久しぶりに、古いアドレス帖を開いて、これもまた古い友人の電話番号を回した。受話器の上がる音と共に、懐かしい声が飛んで来る。
「もしもし、武田ですけど」
「あ、もしもし」
「はい」
「あの、あ、にのみやですけど」
「…あ、あーーーーーーっ、さをり? さをり?」
「うん、そう、久しぶり」
「何よ、あんたは。久しぶりどころじゃないでしょ、行方知れずになってたクセに。何、今どうしてんの?」
電話の向こうから響いて来る声は、昼間話していた終電ツアーのメンバーであった京子だった。受話器から耳を離してもしっかり聞こえるほどの大声は、何年隔てても変わらないらしい。苦笑いしつつ、やっぱり懐かしい声だった。。
ひとしきり昔話に興じた後、私は彼女に尋ねてみた。
「ねぇ、京子。終電ツアーってやったでしょ、覚えてる?」
「覚えてるよぉ、よくもまぁ親にバレなかったもんだよね、いや、バレてたのかな、ただ黙ってただけだったのかもね、みんな」
「あのさ、その、終電ツアーの三人目…」
「薫?」
「あ」
「薫、最初はびびってたくせに、最後の方では一番楽しんでたよね」
「あぁ、薫だ」
「何、あんた。もしかして忘れてたの?」
「…うん。思い出せなくて。薫だ、そうだ、薫だよ」
「…あんたってばどうしようもないね、もうボケが始まってんの?」
「いや、ほんとに、思い出せなくて。顔はね、わかったんだけど。名前がどうしても」
「どうかしてるよ」
「ほんと。どうかしてるね。あぁ、聞かなくてよかった」
「何が?」
「いや、今日ね、薫に会ったの。それがさ、いきなり訪ねてきたのよ。私、薫にここの住所も何も教えてなかったはずなのに。で、私、全然思い出せなくて困っちゃってさ、名前。いやぁ、ほんと、よかった、あなた誰れ、なんて聞かなくて」
「…」
「ん? 何?」
「ねぇ、あんた、大丈夫?」
「え? なんで?」
「薫、三年前に死んだじゃん」
「え?」
「三年前、彼と一緒にバイク乗ってて。ダンプにぶつかって死んだじゃん」
「…」
「あんた、何言ってんのよ」
「…」
「…」
「…いや、そんなこと、でも、だって」
「…」
「…」
電話は沈黙が続いている。窓の外ではいっそう激しく雨が降りしきる。
そうして私は京子の話から知った。薫と京子と私と三人のこと。三年前の大喧嘩。薫の嘘。京子の怒号。私の沈黙。そしてその直後、薫が恋人と一緒にバイクで出掛けた折に事故に遭ったこと。即死であったということ。それを知らされた京子と私はそれぞれの思いを抱えて、葬式以後つきあいが遠ざかっていったこと。そうして自然に距離が生じたまま私たちはそれぞれに歳を重ね、こうして今日に至るということ。
私が思い出したのではなかった。すべて京子との電話で京子の話から知ったことだった。私の記憶には全く残っていない。きれいさっぱり欠落している。薫が死んでしまったという三年前の、その前後の記憶がすっぽりと。
京子は最後まで、薫が来るわけない、薫は死んだんだ、と私に諭すように言い続けた。私は電話を切った後、何度も何度も京子のその声を喉の奥で唱えてみる。死んだ人が訪ねて来るわけが無い。薫はもう死んだ。死んで三年が経つのだ。ちょうど三年前の今頃、彼女は逝ったのだ、もうすでに。
電話を切った部屋、気がつけば壁の時計はいつのまにか真夜中をまわっていた。降り続いてはいるものの雨も先ほどの激しさは消え、小降りになって窓をリズミカルに叩いている。結局あれは誰だったのだろう、昼間訪ねて来た彼女は。流し場には、使い終わったカップとケーキ皿がふたつずつ、汚れたままそこに在る。使った主は私と…。
ひとつだけ。ひとつだけ思い出したことがあった。
傘だ。
多分あれは三人の大喧嘩の前日、薫から話があると呼び出された折に私は、傘を彼女に貸した。青い傘だった。真っ青の無地の傘。その日薫にどうしたらいいだろうと相談され、まるで鉛を無理矢理飲み込まされたような気分に陥った私は何も答えらしい答えを返せないままだった。そして二人帰る頃降り出した雨にも傘などさす気持ちになれず、傘を持ってこなかったという薫に無理矢理、自分のその傘を持たせたのだった。喘息持ちで、私より10センチも小さな、小さな体の薫に。
その時の話の内容はもちろん、次の日したという大喧嘩についても何一つ思い出せないけれど、ただひとつ、そのことだけ私は思い出す。薫について、薫というかつての友人について。あの日見送った青い傘をさして歩く小さな後姿を。
記憶から抜け落ちた彼女はもう、戻っては来ることは、ない。
そして振り返れば、玄関の脇には三年前に薫に貸したままになっていたはずの真っ青な傘が今、ひっそりと佇んでいる。
(写真・言の葉:にのみやさをり)