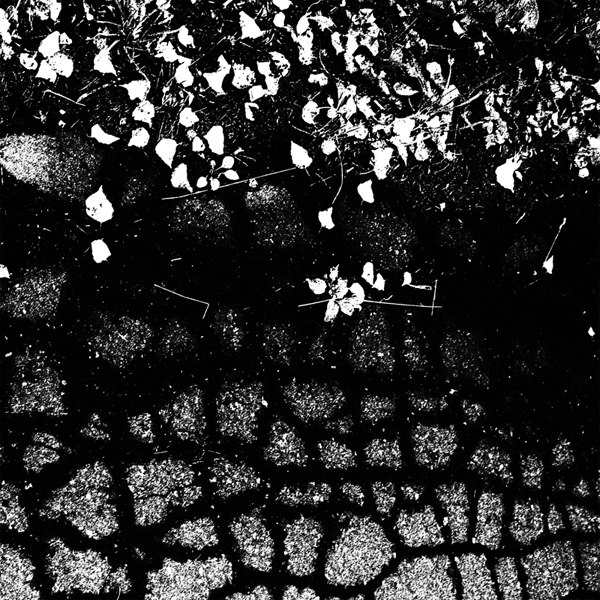
第6章
夜十時を回った辺りから、突然降り始めた雨がいっこうに止む様子も見せずに降り続いている。窓の上に掛けてある時計を見ると、もう午前三時になろうとしている。
昼間、孝子に言われたことが妙に引っ掛かって、約束した心理学のノートを整理し始めたもののなかなか集中できない。千代乃はいったん机の上に開いていたノートを閉じると、煙草に火を付けた。
そもそも千代乃が祖母のもとに預けられることになったのは、千代乃が父親のことを父と呼べなかったからだったと母から聞いたことがある。確か千代乃が家族のもとへ戻ってきてすぐの頃だった。そのとき母と千代乃との他に誰が周りにいたのか、記憶には残っていないが、母が言ったその言葉は、はっきりと今も千代乃の耳の奥に溜まっている。千代乃が生まれて間もない頃から父の単身赴任で二年の間別々の生活をしていたせいか、毎週末車を飛ばして赴任先から帰ってくる父親に抱かれても名前を呼びかけられても、どうしても父さんとは呼べなくなってしまった千代乃のその様を見て、今度生まれて来る子供が同じようになっては大変だとずいぶん気をつかったということを続けて母は話していた。
理由を知らずに祖母と過ごした三年間は、実に忙しい毎日だった。他愛ないいさかいや笑いがたくさん詰まっていて、いつになっても思い出し笑いが消えない。
千代乃は、雨音が聞こえてくる網戸の向こうへ吸い込まれるようにして消えてゆく煙草の煙を見上げながら、家族と話をしないのかと言ったあの昼間の孝子の言葉を改めて思い出してみた。三年の空白の後、家族のもとへ戻ってみると、共働きの両親と弟とが織りなす毎日はあっけないほど規則正しい約束ごとの繰り返しだった。そこへ舞い戻ってきた千代乃にももちろん、家族の一員としての役割分担がまわってきたわけだが、それは、働く母親の代わりの毎日の家事で、それをきちんとこなせば、後は大した問題もなく過ぎてゆく。いさかいも食い違いもない代わりに、誰と向き合うこともなく毎日を過ごしてゆくのだ。
気がつくといつも、祖母との生活を恋しがっている自分がいた。でも、恋しくなればなるほどそれは封印しなければならない記憶に思えてしまい、もがいていたことを千代乃は思い出す。でも、そうしているうちに結局は馴れてしまったのかもしれない。今日改めて孝子に言われるまで、今が自然、これが当然なのだと思い込むようになっていた。
そんな自分にとって、祖母が病気になり世話人が必要になったことは、考えてみれば好都合だったに違いない。あの海の香りがする家にいたいと繰り返す祖母の言葉を楯に、入院させておくという父や母に猛烈に抗ったのも、結局は自分の方があの場所を欲していたからではなかったか。千代乃は、祖母の命が擦り減ってゆく隣で眠りながら、実は自分がその命を吸い取って満たされていたのではなかっただろうか。
千代乃は、短くなった煙草をもみ消すと階段ができるだけきしまぬよう忍び足で階下へ降りた。作り置きのシチューを温め直し、買い置きしてあるパンやらクッキーやら、目につくものすべてをどんどんテーブルに並べてゆく。最後に冷蔵庫から麦茶のポットを取り出すと、千代乃は席に座り、やにわに食べはじめた。
温かいシチューと白い食パンとが次々に胃の中に放り込まれてゆく。胃の中で折り重なるその上にまた、クッキーを麦茶で流し込む。一人きりの食卓はいつでも、こうして何かで埋めておかないと、テーブルが広すぎて逆にその広さに押しつぶされそうに見える。皿も、一つきりよりたくさん並んでいるほうがいい。食べ散らかしたテーブルであっても、何もない空っぽのテーブルよりはずっといい。決して家族四人が揃うことのない食卓で、千代乃は一人、次々にクッキーや菓子パンの袋を破いては食べていった。
新しく開けたはずのクッキーの箱がすっかり空になってしまったことに気づいて、千代乃は慌てて片付け始めた。大した音はたてていないつもりだったが、夜中に食べていることに何となく気づき始めている母が突然起きてこないとも限らない。千代乃は、テーブルいっぱいに散らばった小袋を両手で掻き集めると、ごみ箱にそのまま突っ込んだ。身体をそうやって動かすたび、膨らみ切った胃が、きりきりと音を立てる。
胃を押さえながら、千代乃は降りてきたときと同じように忍び足で二階へ上がると、洗面所の明かりを付けた。扉を開けると降り続いている雨の音が急に大きくなったように耳に飛び込んできた。明かりの中に浮かぶ白い便器の前にまた屈み込むと、はちきれんぱかりになった胃袋をひっくり返すような勢いで吐き始めた。
胃は膨らんでいたものをひっくり返されることに悲鳴をあげ、細い食道は無理矢理大量の汚物を通さなければならないことに悲鳴をあげる。それに構わず、とにかく吐いてしまわなければならない。千代乃は指を奥へ突っ込めるだけ突っ込むと、喉をかき開いた。
すべて吐いてしまわなければならない。それが馬鹿げたことと分かっていても、そうしなくては気が済まない。千代乃の脳裏にだんだんはっきりと母の横顔が浮かんできた。自分を生んでおきながら人の手に預け、また勝手に呼び戻し、そのくせ決して向き合ってくれない母の顔は、どうしていつ思い浮かべても同じ横顔だった。千代乃はいっそう喉の奥へと指を突っ込んでみる。消化されないまま追い出されてくる食べ物が、狭い食道でもんどりうっているのが分かる。いつか千切れてしまうのではないかという怖さが、千代乃の指にさらに力を込めさせる。
こんなことをしても何にもならない。そう思いながらも吐かずにはいられなかった。吐いて食べて食べて吐いて、そうして母の知らないところで自分の身体をぼろぼろにすればするほど、母もそれによって傷ついてゆくようで嬉しかった。自分を生んだのは間違いなく母なのだ。手放すのはいい、突然また呼び戻すもいい。でも、一緒にいるのならせめて一度はちゃんと向き合ってほしい。どうしようもなく助けを求めたときくらい、振り向いてほしい。でもいつも、千代乃に見えるのは母の横顔だけだった。生理が止まったと言ったときも、母は疑いの視線を向けただけだった。何もしてくれなくてもいい。でもちゃんとこっちを向いて、ちゃんとこっちを見て。
赤い染みが胃液に混じって白い便器の中に吸い込まれてゆくのに気づいて、千代乃はようやく喉から指を外した。雨はいつの間に小やみになったのか、もうまばらにしか音は聞こえてこない。千代乃は立ち上がって洗面所で手を洗った。石鹸で泡立てては洗い流し、流しては泡立て、手の甲に汚物の匂いがこれっぽっちも残らないくらいにしつこく洗い流す。そうして正面の鏡に映っている自分の顔を見つめた。母が生んでくれた身体を自分の手で傷つけてゆく。そうすることで自分だけでなく母も傷ついてゆくのだという、そんな馬鹿げたことしか考えられない自分の顔は、あまりにも惨めに見えた。